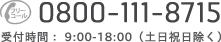行動科学
NPO法人日本交渉協会副理事長 土居弘元
経済学の領域で「行動経済学」が広く認識され始めている。きっかけとなったのは2002年にノーベル経済学賞をカーネマン教授が受賞したことによる。2000年頃はカーネマンの名前を知っている日本の経済学者は少数派ではなかっただろうか。その研究は、認知心理学の応用として合理的な選択を人はするものだろうか、について考えるものであった。いわゆる実験によって実証するという心理学の方法を適用するものである。同じ認知心理学の研究者であるトヴェルスキーと共同研究をし、論文も共著として相当数発表しておられた。掲載される雑誌も“Psychological Review”や“Science”であったが、“Econometrica”や“The American Economic Review”、“The Journal of Business”のような経済学系の研究誌へと移っていった。経済活動をするのが人間であり、その基礎となるのは生身の人間行動であるという考え方によるもので、妥当な考え方である。人間が行う選択は、考えることの中に枠が作られていて、すべて自由な発想の中から選択が行われるのではないということを実験で示そうとするものであった。つまり「合理的な思考にも限界がある」という考え方であり、H. サイモンが示唆していた限界がある合理性という考え方を実験で証明したものなのである。そのような人間行動を新たな枠組みを作って考え、それを経済学のなかに組み込んだということがノーベル賞という形で認められたのである。研究者にとって、それは経済行動や経営行動の研究に新たな道をつくるものであり、喜ばしいことにその流れは広まりつつある。マーケティング研究の大御所的存在であるコトラーは「カーネマンの研究もマーケティングの領域の研究である」と述べている。しかし、これは急に花開いた現象ではないことを述べたいと思う。
このような形で、心理学を人間行動に関する領域に応用しようとする流れは従来から行動科学(Behavioral Science)という名称で行われていて、経済学にも経営学にも一部では相当に影響を与えていたことである。私が経験したことを中心に語ってみたい。
1960年代の半ば、私が大学院の商学研究科修士課程に入った時には、ほとんどの先輩が行動科学の重要性を語っていた。しかし、その内容に関してはあまり語られることがなく、当時カーネギーメロン大学の研究者がその領域で活躍していることが伝えられるだけであった。その中で誰もが読むべき本として取り上げられたものがサイモンの著書『経営行動』とサイモンと心理学者マーチとの共著『組織』であった。ただこれらの本を輪読しましょうという大学院生の活動はなく、また授業で取り上げる先生もおられなかった(当時の大学院における修士課程の授業は講義形式か、評判の本を輪読するという形式がほとんどであった)。仕方がないので、エアコンの良く効いている日比谷図書館へ『組織』を持ってひと夏通い、「ああ、解らないな」と嘆いてアパートに帰りガックリしたことを思い出す。十分な基礎知識もない若者にとって直接飛びついて理解できる内容ではない、ということを後に読み直してみてしみじみ感じた。そのほか、経済学者サイアートと心理学者マーチの共著『企業の行動理論』という当時評判の書を、ある授業で先生に頼み込んで輪読の対象として取り上げてもらった。経済学の行き方とは違うなあ、と感じたことを思い出す。
行動科学に関心を持ったのはこの頃までで、行動科学の領域から離れてしまった。規範的な方法で意思決定を考えるH. レイファ教授の「決定分析」に魅せられて、これをズッとやってみようかなという思いに駆られたからである。1人で本を読み、研究誌の論文を読み進んでいくのはなかなか大変なことであった。そのような状況を打破できたのは34歳の時、MITにおける2週間のサマープログラムに参加する機会を得ることができたからであった。そこで得た多属性効用関数の理論の知識は私の生涯を決めた理論である。その後、藤田先生の「交渉に決定分析を結びつけてみないかい」というお話で交渉を研究する方向も考えて文献検索をしてみた。そして交渉研究をしている研究者に、行動学に基づく意思決定理論の領域から出発しておられる方がかなり多いことに吃驚した。
現在では交渉研究のメッカ的存在になったハーバード大のPON (Program On Negotiation)を訪問した時、案内してくださり、いろいろとお話をしてくださったルービン先生は心理学から交渉学へと進まれた方であった。沢登りが趣味のルービンは岩から落ちて亡くなられた。50代半ばのことであり、今でも残念な思いである。
『交渉の認知心理学』の著者であるベイザーマンやニールも心理学畑の出身であり、今では交渉学の領域で名をなしている。そのほかにも、行動学の視点から意思決定の問題に取り組んでいる研究者を多数擁立しているのはペンシルバニア大のウォートンスクールやシカゴ大のビジネススクール、またそれを交渉学に特化させているノースウェスタン大学のケロッグ・ビジネススクールと付属のDRRC である。
人間行動である限り、意思決定や交渉だけでなく、金融や財政の問題もかつての経済学だけで考えることが難しくなり、行動経済学のアプローチから新領域が開拓されているようである。しかし、そこに心理的な側面をどれくらい組み込んで考えるのがよいのか、となると判断は難しい。枠組みとしてはハードな経済学や経営学の枠組みを据えて、それを保持しながら、新たに行動学の成果を組み込みながら進めていく。いずれはその流れが経済学に深く浸透するのではないか、と考える次第である。
土居 弘元氏
国際基督教大学 名誉教授
特定非営利活動法人 日本交渉協会副理事長
1966.3 慶応義塾大学経済学部卒業
1968.3 慶応義塾大学大学院商学研究科修士課程修了
1971.3 慶応義塾大学大学院商学研究科博士課程単位取得退学
1971.4 名古屋商科大学商学部専任講師から助教授、教授へ
1983.4 杏林大学社会科学部教授
1990.4 国際基督教大学教養学部教授(社会科学科所属)
1995.4 教養学部における一般教育科目として交渉行動を担当
2007.3 国際基督教大学を定年退職(名誉教授)
2007.4 関東学園大学経済学部教授 現在に至る
【著書・論文 】
『企業戦略策定のロジック』中央経済社2002
「価値の木分析と交渉問題」“Japan Negotiation Journal”Vol.2 1991
「交渉理論における決定分析の役割」“Japan Negotiation Journal”Vol.16 2004
その他のレクチャー
土居弘元先生による交渉学Web講座
土居弘元先生による交渉学Web講座
土居弘元先生による交渉学Web講座
「交渉行動と意思決定」という授業を担当していた頃、第1回目に行うロールプレイングは「マウンテンバイク」であった。これは、引っ越ししなければならなくなった高校生が、愛車である中古のマウンテンバイクを売るという話である。大学2、3年生にとってはそれほど違和感を覚えるケースではない。そこで行われるやり取りと結果を見ていると、売り手は「できるだけ高く売りたい」という気持ち、買い手は「できるだけ安く買いたい」という気持ちに基づいて行動する学生が多かった。